書評:力と交換様式〜交換が世界を動かす力である〜
書評と書くのはおこがましいけれども、あまりにも面白い本だったので少し引用も交えながら書いてみようと思いました。
これまでに記事にしてまでまとめたことがあるのは下記の"THE GREAT CEO WITHIN"だけな気がするけれども、この本も非常に素晴らしかったけれども、どちらかというと実践的なビジネス書としてはベストと思えるぐらい素晴らしかったです。

今回の力と交換様式はいわば世界の見方が少し変わる本といっても良い本です。日常の出来事、世界史の構造を少し違った角度で解釈できるようになる、自分の思考・世界に対する解釈の幅を広げてくれた本でした。少しでもこの面白さが伝わればと思ったかつ自分の思考のまとめとしてもなるかなと思い書いてますが、なんぜボリュームが多いので上手く伝わるかは不安です。
ただぜひこれを読んで本に興味を持った方は実際に読んでいただければ幸いです。
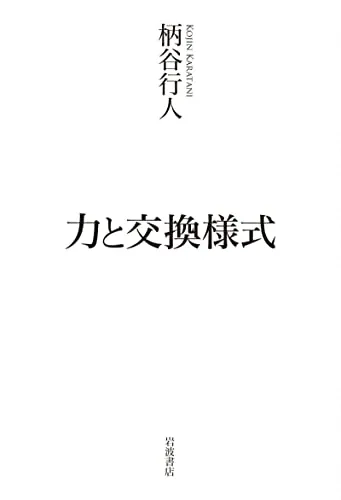
世界を動かす”力”とは
題名の通り”力とはどういうところから来るのか”というのを交換様式からなのではないかということを書いてきている。
そもそも世界を動かしているのは何なのか?その力の源泉は何なのか?力とは何なのか?ということはふと立ち止まり考えると面白い問いであると思う。人の意志が世の中を動かしているというのは簡単だけれども、その意志っていうのは誰の意思なのか?
世を動かす力というものを俯瞰して考える機会は少ないがこの本はそこに対して1つの考え方を提示してくれる。
この本においては、まず前提とあるのは交換という行為には霊的な力が宿りそれが力となって動かしているというのが主張である。(モースの贈与論のハウに近い)そのような交換様式から生じる力を軸に人類史の歩みを再考している。
これはマルクスの資本論を経ての考え方であり、マルクスの生産様式で人類の歴史を”原始共同体、奴隷制、封建制、資本主義、社会主義”と定義した唯物史観に対してそれを交換様式から試みたと理解している。
生産様式:土台である経済の仕組み(下部構造)によって社会的側面を規定するもの
著者によればマルクスの資本論では物象化(人間と人間が物と物の関係のように扱われること)が主に取り上げられてきたが、つまり商品の価値を物神(フェティシエ)・霊的な力に見出していることを見落としていると言及している
”机はやはり木材、ありふれた感覚的なものである。ところがこれが商品として登場するとたちまち、感覚的でありながら超感覚的な物に転化してしまう。それは自分の脚で立つばかりでなく、他のあらゆる商品に対しては頭でも立っていて、ひとりで踊りだすときよりもはるかに奇怪な妄想を、その木頭からくりひろげる。したがって商品の神秘性は、その使用価値に由来するものではない。価値規定の内容から生じるものではない” (資本論)
この霊的な力は、前述のように交換という行為から生じるのではないかと考えて著者は交換様式を論じている。その交換様式については下記の4つがあると提示されている
A:互酬(贈与と返礼)
B:服従と保護(略取と再分配)
C:商品交換(貨幣と商品)
D:Aの高次元での回復
そして歴史的な推移とともに世界を動かす力というのはAから始まり、BとCへと移行していくのだが、Dへの回帰・回復が将来の姿ということを説いている本である。少し各交換様式を説明しながら要約していこうと思う。
交換様式の変遷:A呪力→B権力→C資本
A:互酬(贈与と返礼)
これは自分の捉え方だとモースの贈与論そのままである。原初人間社会においては定住化とともに交換が始まったとされている。交換には返礼の義務が生じることは下記の文章からもわかる。互酬という交換様式による力がここにはある。
贈り物というのは、したがって、与えなくてはならないものであり、受け取らなくてはならないものであり、したがってそうでありながら、もうらうと危険なものなのである。それというのも、与えられる物それ自体が双方的なつながりをつくりらすからであり、このつながりは取り消すことができないからである(贈与論)
この返礼の力っていうのは日常生活でも感じることだとは思う。いわゆる貸し借りの感覚。なのでそれを力と言うには少し違和感はあったが、確かにこのなにかわかないけれど負う感覚というのは霊的な力と呼んでもいいのかもしれない。
(少し違う観点からの話だが、こういったときに古代にさかのぼって考える意味がどのくらいあるのだろうかと考えたけれども、結局人間という存在は変わらないので人間がどういうような力で動いてきたかという観点に立てば、古代に遡るというのは非常に合理的な思考方法であると思う)
B:服従と保護(略取と再分配)
そしてAの次に発達していく力というのがこのBの力。現代でいう”国家”や”会社”の中において感じる力に近い。ただ面白いなと思うのが、この力というのは上から生じるように思えるが下からも生じる力であると論じているところ。
国家は支配階級と被支配階級の交換、被支配階級の自発的服従によって生じている
国家の成立にとって必要なのは、奴隷ではなく、いわば”自発的に服従する奴隷”つまり臣民(subject)である
つまり、どちらかからの一方的なベクトルで成り立つものではなく、交換であるということを論じている。Aの互酬制が水平的ならBは垂直的な互酬制といえるかなと。
会社に見立てるとたしかに交換っぽい文脈は納得はする。会社に自発的に支配されることで、保護されることと交換されている。毎月給料は入ってくるし、その代わり会社の言うことを聞かないといけない。逆に会社からすると保険・給料含めて守らないといけない。なので双方向な交換様式がここにはあることは感覚的にも分かる話ではある。
では、AからどのようにBへ変化していったのか
Aは氏族社会の特徴。氏族社会において重要な交換は、物の交換ではなく人の交換、すなわち婚姻である。
娘ないし息子を別の集団に贈与し、且つお返しを受け取る。それが外婚制である。親族構造が形成され、より大きな氏族共同体が形成されるのにいたったのは、このような交換を通じてである
そうしてある程度人数が増えてくると氏族は部族として分散して成立するようになり、それは絶え間ない戦争も引き起こした。Aである限り水平的な力関係であるため、垂直的な力は生じない。それは族長・首長になったとしてもそこは水平的な力のためすぐに崩壊する可能性が高い。
贈与の互酬交換が必ずしも友好的・平和的なものではないからだ。それはしばしば競合的であり、戦争に転化する可能性があった。たとえば贈与はポトラッチ(儀礼的な贈与競争)に見られるように、返済できないほどの過度の贈与によって相手を圧伏させる手段となる。しかも、それは相手を支配するためではなく、自らの威信を守り誇示するためになされる。したがって互酬交換は(中略)戦争をもたらすことが少なくない
ここで著者の論が個人的に面白いなと思えたのは、いわゆる部族の乱立と戦争によって国家が徐々に成立していったというのは間違いなのではないかということを指摘している点。そういった社会はまだAの社会の延長上であり、武力制圧ではBの交換様式に転換しないと論じている。
ではBに変化するためには”聖なる王権”が必要としているらしい。つまりウェバーのいうカリスマ的支配ということが必要だということを説いている。
軍事的征服は相手を物理的な力によって抑えるが、それだけでは、相手が自発的に服従することにはならない。それを可能にするのは、物理的な力だけではなく、交換様式Aに伴う霊的な力を更に上回るような霊的な力である。(中略)それのみが王に、首長を超える力を付与する
このあたり正直少しピンときていない自分もいるが、なんとなくは理解できる。Bの状態というのは交換であって一方的なベクトルではないはず。そのためには何かしらの力と呼ぶべきかなにかが必要。それが王であり単なる首長でないもの。
だからこそ王には神話が必要であり、カリスマ的であることを双方が求めた結果生まれたのがBという交換様式であり、国家というものなのかもしれないと理解している。なので何が王を創ったのかというのは面白い問いではあるなと思った。スタートアップ業界において創業者は特別という感覚はあるが、その創業者の力というのもある種”聖なる王権”の力というものが生じているのではないかと思う。
C:商品交換(貨幣と商品)
これはすごく直感的にわかる交換様式であるとおもうので、そこまで説明はいれないが現在も行われておりこの延長における資本主義の力というのは現状一番大きい力であることは間違いない。
マルクスは「貨幣物神から資本物神への転化」について、つぎのように述べた。貨幣は物と交換できる力を持つ。そのことが貨幣を蓄積しようとする「絶対的な至富衝動」をもたらす。(中略)たんに溜め込むだけでなく蓄積しようとする資本家が生まれる。資本家は合理的な守銭奴である
かといって著者によればBの力のほうがまだ近代以前では強かったことを説いている。CはBの力を強め帝国という巨大なBをつくっていったことを論じている。
そして現在においてはこのCの力が一番強い交換様式として残っていることは日々生活していても感じることであることには間違いないであろう。
そしてこの力を高めていくために産業資本主義というものがいかに生じていったかも、プロテスタンティズムの倫理と資本主義の精神の説明も本書ではじっくりわかりやすく書いていただいているが長くなるので省略、ぜひ興味ある方は本書を読んでいただければ・・
このように"A呪力→B権力→C資本"のように力が動いていったことを論じている。で、ここまではギリギリわかる歴史感である。著者はこの整理で終わらず、Dという交換様式が存在した、また今後存在しうると考えているところを論じている。
D:Aの高次元での回復
Dについて著者下記のような表現を用いて説明している。
Dは、Cが支配的となる資本主義社会のあとで出現するような社会の原理だといってよい(中略)Dはいわば、BとCが発展を遂げた後、その下で無力化したAが”高次元”で回帰したものだ。注目すべきはそれがすでに古代において出現していたということである。
つまり、Dというのは今私達が生きている社会(BとCの発展)のあとに出現するのを予言しつつも古代にもあったという。ちょっとわけがわからないと思うが、一度実はDというものがあったという。それを原始宗教・普遍宗教に見出している。
古代に各地で起こった普遍宗教的運動は、外見は様々であるが交換様式BとCに抗して、Aを”高次元”で回復するDの強迫的到来である。
そのような運動において、イエスや墨子の例がわかりやすかったので下記で引用している。
イエスは王・国家を斥けた。交換様式でいえばBを斥けた。イエスは家族・共同体を斥けた。つまりAを斥けた。イエスが唱えた最も重要な掟は、隣人愛:隣人を自分のように愛しなさい。 隣人とは社会的初関係を超えて見いた出されるような他者のこと。彼が示唆するのは交換様式ABCを超えて人と交わること、それがDの到来であり神の国の到来である。
孔子のいう仁とは差別的である。家族や長たるものを大切にする偏愛でしかない。墨子のいう兼愛は恵まれないものへの愛を説くもの。古代において各地で起こった普遍宗教的運動は次の点で共通している。交換様式B・Cに対抗してAを高次元で回復するDの強迫的な到来である
正直面白いけどわかるようでわからないというのが本音である。交換様式A・B・Cだけで十分に説明がつくはずだったのだけれども、そこで説明しきれない力を筆者は見出したのだと思う。
Dの力を考える経緯には”ネーションの成立”についても本書の中では記載がされており、このネーションという力が何だったのかについての考察がヒントにはなると自分は考えている
ベネディクト・アンダーソン想像の共同体:ネーションは共同体が解体された後に想像的に再建された概念である。まあそれを推進したのは、資本主義経済の成立、印刷を通じた情報技術の発展。
ネーションを形成したのは2つの要因。中世以来の農村が解体されたために失われた共同体を想像的に回復しようとした。もうひとつは絶対王政の下で臣民とされた人々がその状態を脱して主体として自立したことである。ネーションはAの低次元での回復である。
つまりB・Cの力が強くなっていったところに、Aの農村的な共同体が解体されたが、しかしフランス革命など含めて歴史を考えると別の力が働きはじめた。それを想像の共同体とし、その力の源泉はAの低次元での回復として見なしたのである。その力についてDのヒントを見つけたのではないかと思う。
またDについて考えざるを得なかったのはマルクスの資本論の影響は大きいのではないかと思う。そこで出された問いは、現代社会における考えないといけないものなかもしれない。著者によればこう書いてある。
最晩年のマルクスは、ある意味で、共産主義を太古からあり且つ中断されていた道の回復としてみていたからだ。(中略)共産主義とは古代社会にあった交換様式Aの高次元の回復である。つまり交換様式Dの出現である
資本によってあらゆるものが商品化され、資本の論理に「包摂」されていってしまっている。この力の前に人々は別の力を求めていると説いてその答えとしての共産主義・コミュニズムというものをマルクスは考えていたように、著者もそのDの力を見出したのだと考えている。
Dの到来と著者の警告
前述したようにDというのは資本主義の力が大きくなったときに生じる力である。まさに今・現在の状況と近いのではないか。
トマスピケティの”21世紀の資本”において、資本主義が今後も存続するために、資産に対する世界規模での累進課税・ベーシックインカムなどを提言している。これは資本主義に変わるものではなく、交換様式BとAを全面にだすことでCを養護し維持しようとする動きである。
しかし著者はこのような考え方には下記のように否定的である。
このような社会改革案に共通するのは資本主義経済を人間の意思によって操作できるという考え方である。しかし資本や国家の力は物神や怪獣のような力であり、人間の意思を超えている。
そしてこのような警告もしている
資本はなんとか新たな差異を見つけ出す。それが困難になったときは国家=ネーションが動員される。つまり国家の経済政策が代わり、さらに対外戦争にも至る
まさにこれは世界大戦時におこったことではないだろうか。そして目下の今の世界を見てもこのようなことが起こっていることは自明である。国家や資本から生じるBやCという交換様式の力はコントロールすることが難しい。
では、どうしたらいいのかという結論がこの本にあるかというとない。しかし予言はありこの本の最後はこう締めくくられている。
交換様式でいうB・Cの力を放棄することはできない。(中略)唯一可能なのは、Aに基づく社会を形成することである。が、それはローカルにとどまる。BやCの力によって抑え込まれ、広がることができないからだ。ゆえに、それを可能にするのは、高次元でのAの回復、すなわちDの力によってのみである。ところがDは、Aと違って、人が願望し、あるいは企画することによって実現されるようなものではない。それはいわば、”向こうから”来るのだ。(中略)今後に、戦争と恐慌、つまり、BとCが必然的にもたらす危機が幾度も生じるだろう。しかし、それゆえこそ、”Aの高次元での回復”としてのDが必ず到来する、と。
この本の面白さをなんとかして伝えたいという思いにかられて、書評と呼ぶには少し内容が薄い気もしますがあまりにも面白い内容で密度が濃かったのでどうにかして自分の頭の整理としてもこれは書きたいという思いで仕上げました。
Dの力というものが具体的になんなのか宗教という力でもないとおもうし、コミュニズム的な私有財産を廃止し、生産手段を共同所有にすることによって、労働者階級を中心とした平等な社会を実現するという話でもないとは思う。
しかしこのDについては例えば人新世的な考え方もあると思うし、それは今の環境社会・脱炭素的なことを考える力なのかもしれないし、資本主義ということは生き残る前提で、しかし何か他の力というのを人々が探している感覚はたしかにあります。
もしかしたらAの高次元の回復というのは、DAO的な要素の意味合いもあるのかもしれないと思ったり、宗教でなくアルゴリズムに王権を被せた分散化社会ということなのかもしれないなと妄想したりしていました。
この本を通して世界の見方が少しだけ変えることができ、非常に面白かったです。自分の拙い抜粋だけでなく、これ以外にも本当に面白い文章が詰まっているので気になった方はぜひ読んでほしいとおもうのでぜひ!
Tweet