観光客の哲学:グローバリゼーションとナショナリズムのダブルスタンダード
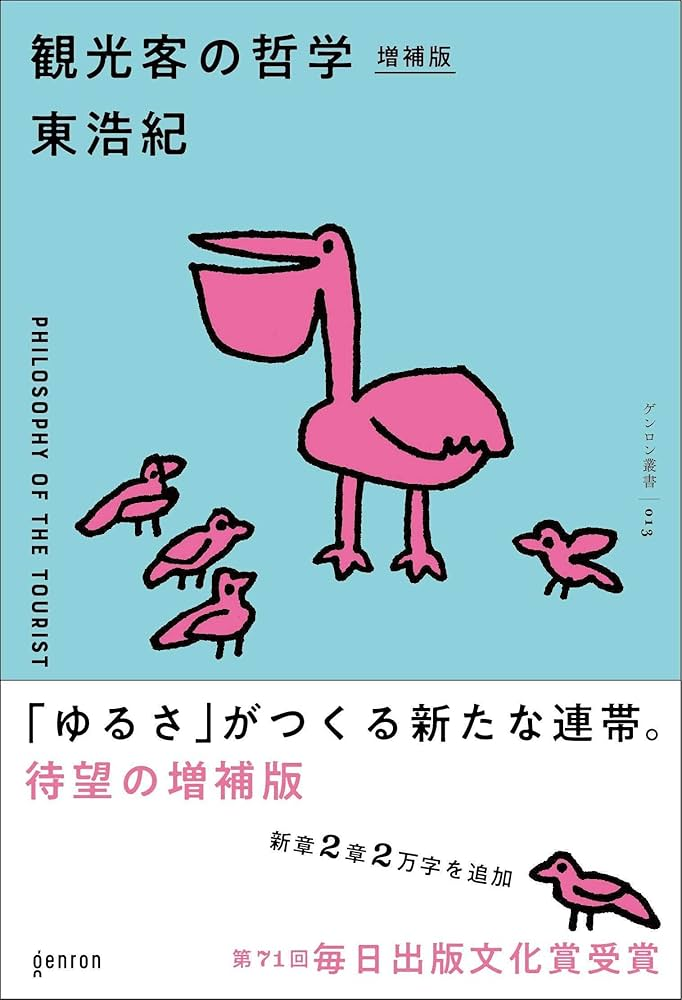
海外に行く飛行機の中で読み終わった。海外に行くタイミングで読もうと思っていてとっていた本。
"観光"ということに対して、自分も考えたいと思っていたところであったし、訂正可能性の哲学という後の本を先に読んでしまったため、早めにこの前のこの作品も読んで置きたいなと思えた。
2020年代に入り、突き進んできたグローバリゼーションからの揺り戻しを感じる。それはトランプの当選もそうだし、戦争のような形でもそうだし、グローバルフラットの世界から変わっていく気配を感じる。しかしそれは自国中心主義、極端な共同体主義をつきすすめていくのは、結果第二次世界大戦などと同じような気配が漂う気がしている。
しかしそんな中でも観光というのはまだできやすい。その観光という意味や、観光産業というものが今後どのようになっていくのかというのをうっすら考えていて、そもそもタイトルで観光客の哲学とあったため購入はしていたが予想を超えて今の自分にとって読むべき本だったなと思う。
観光客という存在が中途半端で不安定で、ふわふわしていることがこの時代においては逆に考えるべき重要なポイントだということが一貫して伝えたい趣旨であったように思う。これはローティーの本質主義の否定にも繋がるはなしで、過去哲学というのは本質を求めてきたが、今のような複雑性が高いような世界情勢においては本質ではなくフワフワとした概念こそ考えるべき存在ということを一貫して伝えているのではないかと受け取っている。
20世紀が戦争の時代であるならば、21世紀は観光の時代であるということは本文中に出てくるが、その観光の時代だからこそ出てきうる思想みたいなのは確かに考えなければいけないような気がしている。
そうしなければ、20世紀の戦争の時代に戻ってしまう可能性がある。グローバリゼーションが進んでいく中で、フラット化していった社会における反発が最近多い。それはナショナリズムへの回帰である。しかし完全にナショナリズムだけに偏ることは21世紀においては起こりづらい。そうなった時にどのような世界秩序、時代秩序が生まれるのだろうか、そしてそれを支える思想にはどのようなものがあるのだろうか。そういったことを考えさせられた良い問いを改めて与えてくれた本だった。