訂正可能性の哲学
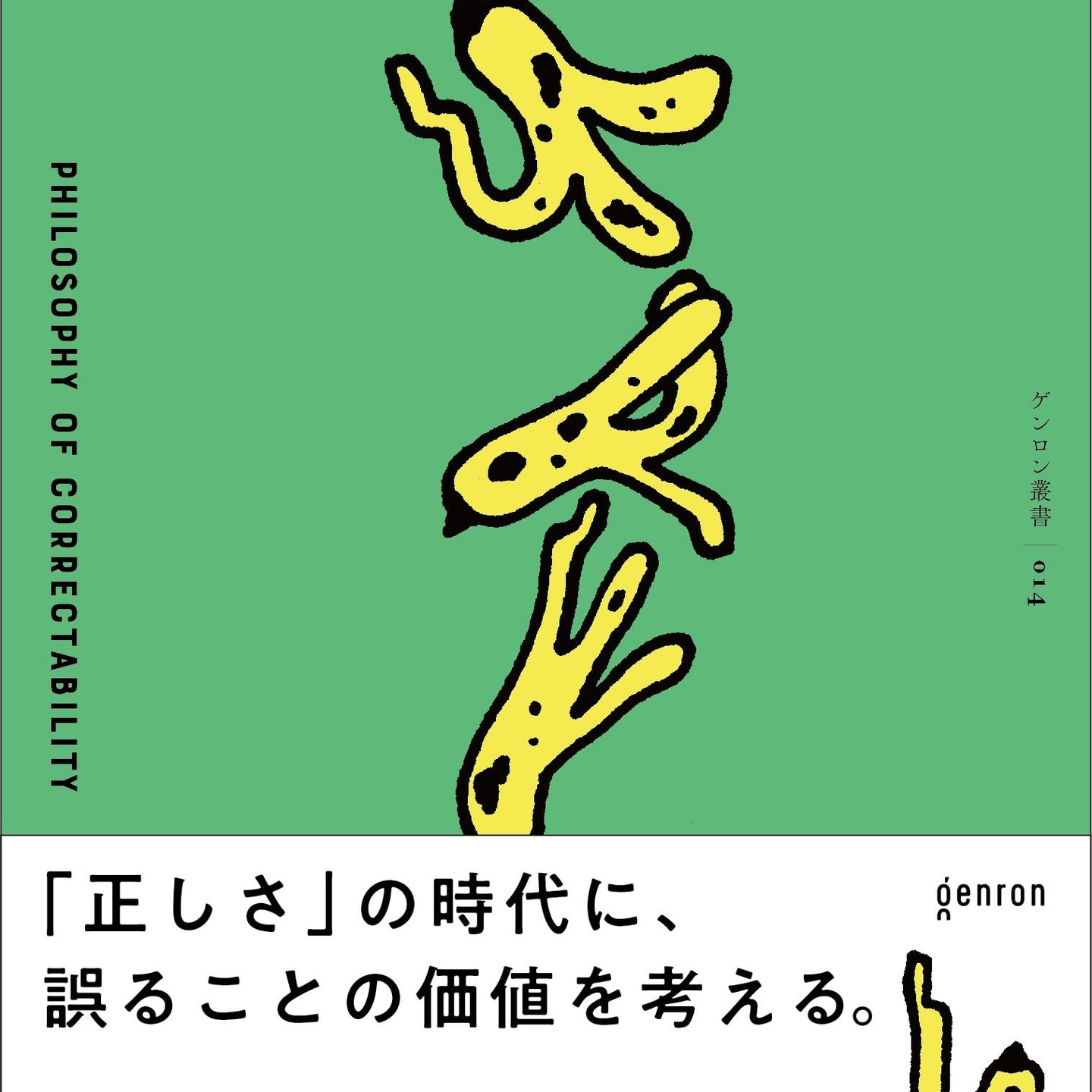
積読していた東浩紀の最新作。
世界のあり方として、訂正可能性というものを失ってしまうとそれは全体主義に陥ってしまいキャンセルカルチャーなどを悪いベクトルで助長してしまうことについて警告をしていると個人的には読み取った。基本的にはどういうように社会の民意や方向性を決めていく決め方において、訂正可能性が大事だということを伝えたいのだと思う。それが元にあるのはリベラルと保守の対立で、そのリベラルの進捗がないことに対する彼なりの焦りであり提言にある気がする。対立を乗り越えていく方法としてこの訂正可能性について、様々な視点から論が展開される。
2010年代は人のことを信じすぎた時代と彼が話しているように、熟議民主主義もすべて人の力を信じすぎたかもしれない。
一方その反動としてAIに監視されたほうがいいという感覚もコロナをきっかけに根付いてしまった。しかしそういったAIによる一般意志をつくるやりかたをしてしまうと、統計・類似のアナロジーで決断がされていく。それが絶対なものとなり訂正のダイナミズムがとりいれられないとなると暴力的な存在になってしまうことを彼は危惧しているのだと思う。
そこでトクヴィルのアメリカのデモクラシーにおいて、小さな結社が自由にできることが民主主義において大事だというはなしをとりあげて、そういった私的な空間での会話の数を増やして、合議によって政治的な正しさをはかるのではなく、そういった私的空間での対話が一般意志(AI)に関わることによって訂正を繰り返していくことによって社会を進めていくことを提言している。
何が正しいのかというのが動的であり非常に分かりづらい時代に入ったなと前から思っている。それは絶対的な正しさがないという議論づけで終わってしまうのではなく、去年読んだ[偶然性・アイロニー・連帯]のローティーがいったような、本質主義におちいらなく会話を続けることが大事という議論に近いなとおもったし、千葉さんの勉強の哲学における享楽さにも近いものがあるなとおもった。
一方ではどうやって私的な会話が訂正可能性に転じるのか?例えば今フジテレビの議論が活発だが民意をSNSの言葉にしていいのかというとそういうわけではないと自分は思っている。テーマとしては理解しうるしいいなとおもういっぽう実際問題社会でどうこういう訂正可能性をとりいれていけるのかは自分含めて考えないといけないのだなと思えた。
Instagram(パーソナル):https://www.instagram.com/nakajish/
X(メディア):https://x.com/nakajish
YouTube(実験的):https://www.youtube.com/@WhatsToCome-cu2zx